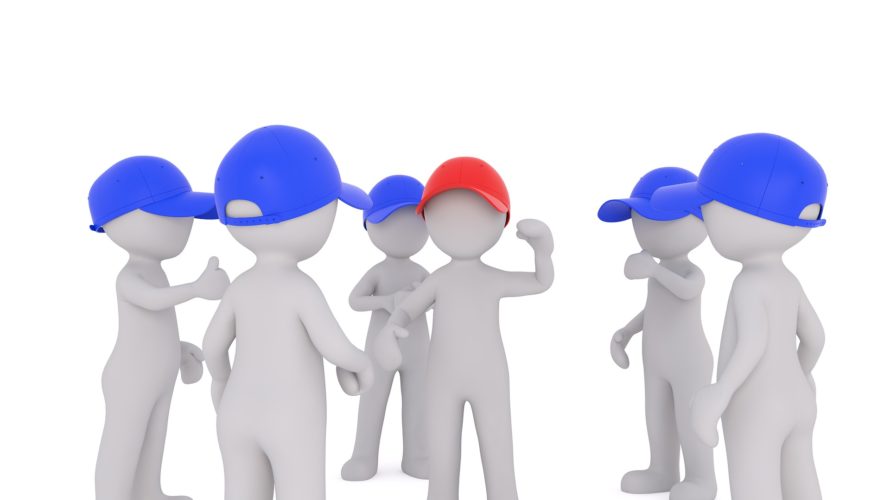「植えないから刈り取れない」適性を上回る実践の力
- 2024.05.24
- リーダーシップ 生き方
- #行わないと得られない, #適性以上, #実践力

「なぜ貧しいのか?」二宮尊徳の教え
江戸時代後期に思想家として活躍した二宮尊徳(にのみやそんとく)氏は次のような言葉を残しています。
遠くをはかる者は富み 近くをはかる者は貧す
それ遠くをはかる者は百年のために杉苗を植う
まして春まきて秋実る物においてをや
故に富有なり
近くをはかる者は春植えて秋実る物をも尚遠しとして植えず
唯眼前の利に迷うてまかずして取り
植えずして刈り取る事のみ眼につく
故に貧窮す
この言葉の意味は、「遠く(将来)を考える人は裕福になり、近く(目先のこと)を考える人は貧しくなる。遠く(将来)を考える人は、百年のために杉の苗を植えるし、秋実るものを考えて春、種をまく。だから豊かになっていく。しかし、近く(目先のこと)ばかり考える人は、春植えて秋に実るなど待ちきれないと考えて植えない。それでいて、目の前の利益に心を奪われ、何も植えないのに刈りとろうとばかりする。だから貧しくなるのだ。」になります。
つまり、秋の収穫の時期になっても刈り取るものがないのは、自分が春に種を撒かなかったからであり、そのことに不満を言ったり嘆いたりしても無意味だ、ということです。
向き・不向きにこだわる人たち
この10年程で、就職・転職市場では「適性に合った仕事」「自分に向いている仕事」に就こうというニーズが高まってきたと思います。誰もが社内での出世競争に挑む時代は終わり、「そもそも自分は何に向いているのか」「どんな仕事が合っているのか」を見極め、より自分に合った無理のない職業生活を指向する人が増えているのでしょう。このことは個の幸せの追求という意味でも、多様な職業観の受容という意味でも好ましい変化だと思います。しかし、実際は適性があってもなくても行えば得られるし行なわなければ得られないことも多くあり、向き・不向きへのこだわりが実践を阻んでしまうケースも見られます。
例えば、よく「自分はリーダーに向いていないと思う」「自分は管理職向きではないと思う」という話を耳にしますが、実際に組織の求心力を上げ業績を上げていくためには、リーダーとなるべき人が周りの人から信頼され支持される行いをしてきたのか、今しているのかという”実際の行い”が非常に大切になります。
この行いはどんな小さなことでも構いません。誠実な姿勢で仕事に取り組んでいるか、感謝や労いの言葉をかけているか、トラブルを抱えた人を助けようとする姿勢があるか、など、日々の小さな行いの積み重ねが信頼に値する人間を形作っていきます。反対に、いかに元々の気質がリーダーに向くものであったとしても、もしそのことに慢心して実際の行いが伴っていなければ周りの人たちから信頼されることも支持されることもないのです。
信頼されたいなら信頼される行いを
人は自分自身の行いの結果を数か月、数年、数十年のタイムラグを経て、後から受けるようになります。二宮尊徳氏は「将来を考えて春に種を撒かないものは秋に貧しくなる」と、特に経済状況について述べていますが、対人関係を含むありとあらゆる現実は、実は同じ原理で私たちが受けている結果だと知る必要があるでしょう。
「自分は果たして種を撒く仕事に向いているのか、それとも向いていないのか」を考えあぐねるより、下手でもなんでも秋の収穫を目指して汗を流して種を撒いてみることが知恵ではないでしょうか。実践には適性以上に現実を変える力があるのです。
-
前の記事

不満を生み出す空気 Vol 1 「私はあなたたちの味方です」 2024.05.17
-
次の記事

意見を言えない空気 Vol 6 「忙しいマウンティング」 2024.06.07